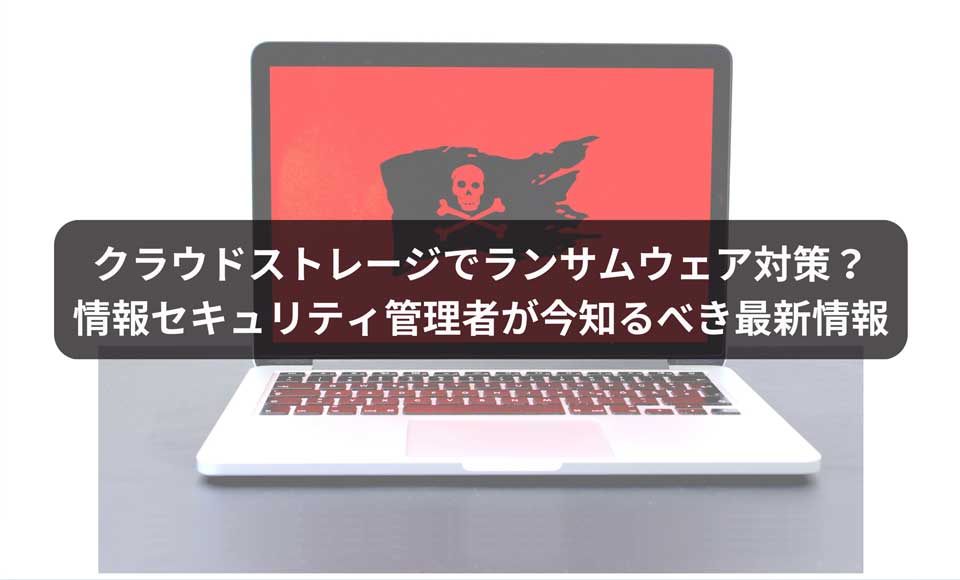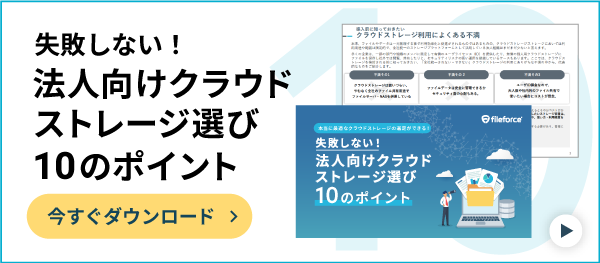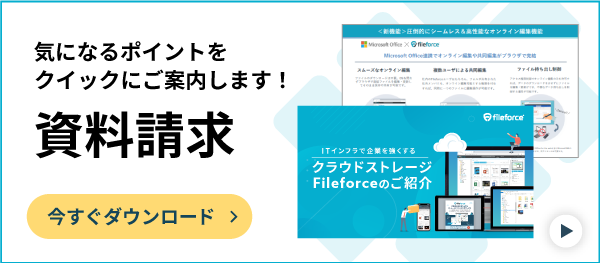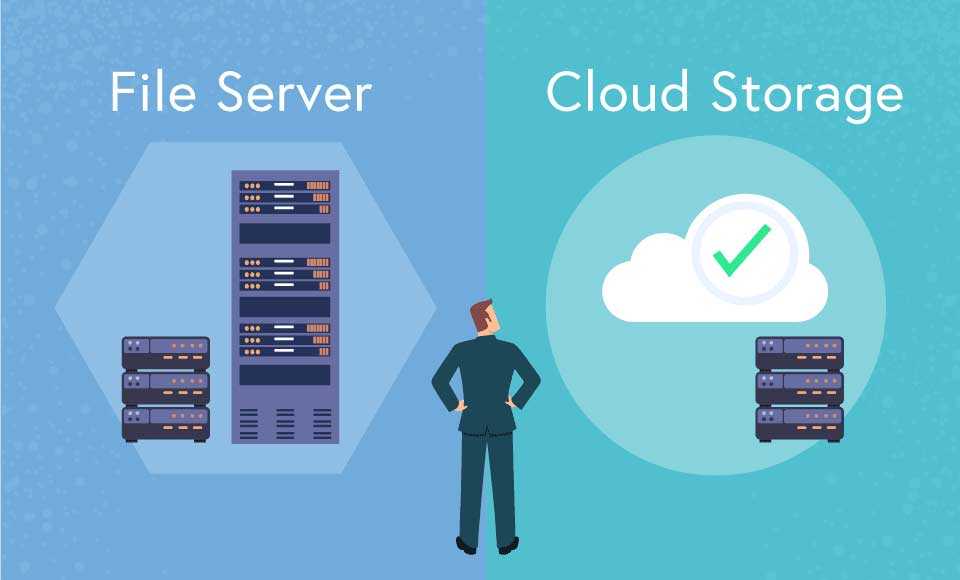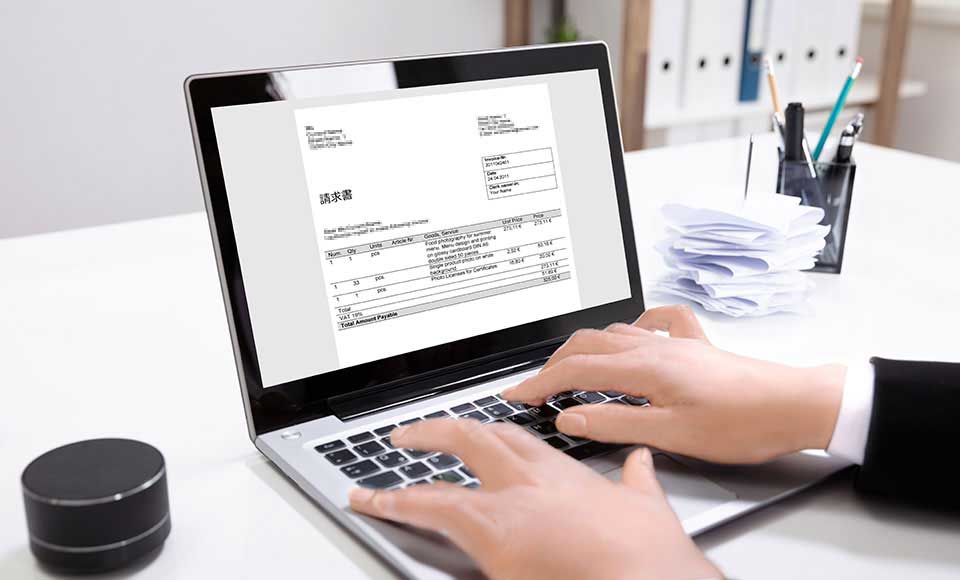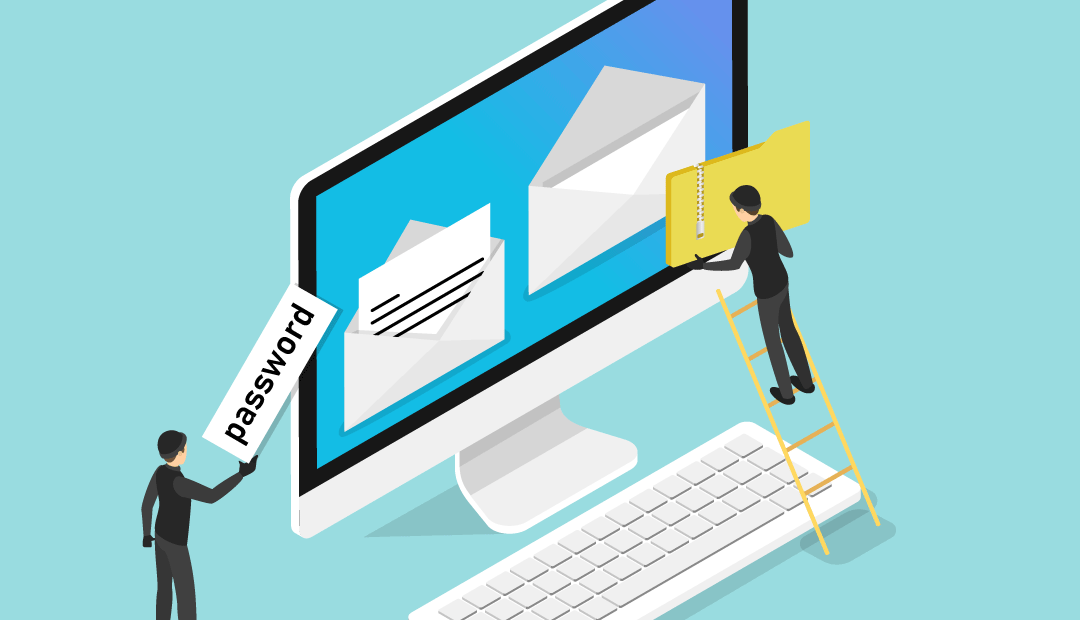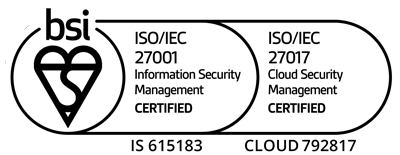NASのセキュリティ強化は必要か?起こりうる問題と対策を解説
- 公開日:
- 更新日:

目次
クラウド化を推進したいけどセキュリティ面が不安...とお考えの方へ
インターネットからアクセスできてしまうと、外部からの攻撃を受けやすくなるのでは?クラウド化したときの安全性はどうなるの?と不安に思われる方もいるかもしれません。
クラウドストレージでのセキュリティ対策についてまとめた資料をご用意いたしました。ぜひご参照ください。
NAS(ネットワークHDD)は組織内でのファイル共有に便利ですが、セキュリティ対策を怠るとさまざまな危険があります。この記事ではNASのセキュリティ強化の必要性と具体的な対策を解説します。データ保全のために、バックアップも取っておきましょう。
クラウドストレージFileforceの資料をダウンロードする。
NASとは?
NAS(Network Attached Storage)は、ネットワークに接続して利用するタイプのHDDです。一般的な外付けHDDのようにUSBで1台のパソコンに接続するのではなく、LANケーブルを通じてルーターやハブに接続し、複数の端末から同時にアクセスできます。社内ネットワーク内で共有できるほか、リモートアクセス対応モデルなら外出先からもデータにアクセス可能です。これにより、ファイル共有やバックアップの効率化が図れ、テレワークなど多様な働き方にも柔軟に対応できるストレージ環境を実現します。
NASでセキュリティ対策が必要な理由
NASはファイル共有に便利ですが、多くの企業でセキュリティ対策が見過ごされがちです。しかし、社内の機密情報や個人情報といった重要データが一元管理されるNASは、ランサムウェアを始めとするサイバー攻撃者にとって標的となります。脆弱性の放置や安易なパスワード設定は、不正アクセスのリスクを著しく高めます。万が一、セキュリティインシデントが発生すれば、情報漏洩による信用の失墜や事業停止など、経営に深刻なダメージを与えかねません。こうしたリスクを回避するため、NASには適切なセキュリティ対策が必要です。
NASのセキュリティ対策を怠るとどうなるか?

NASのセキュリティ対策を怠っていると、どんな問題が起こるのでしょうか?さまざまなトラブルが起こる可能性がありますが、とくに以下のポイントは注意しなければいけません。
マルウェアに感染する可能性
NASがマルウェアに感染してしまい、データを抜き取られたり勝手にデータを暗号化されて利用できなくなったりする可能性があります。
とくに近年は、ターゲットのデータを暗号化して、元に戻すために金銭を要求するランサムウェアと呼ばれるマルウェアが流行しています。
パソコンがマルウェアに感染してしまうと、アクセス先のNASのデータも感染してしまう恐れがあるので、セキュリティ対策は万全にしておく必要があるのです。
情報漏えいの可能性
上述のように、マルウェアの感染でもNASに保存された情報が外部に流出してしまう可能性があります。さらに、社員の操作ミスや内部不正によって情報漏えいが発生するケースもあります。
実際、NASに保存されていた顧客データを企業の関係者が不正に持ち出し、同業他社に渡していた事件も起こっているようです。大勢の利用者がアクセスする環境では、アクセス権限を設定するなどの基本的な対策を怠ってはいけません。
業務データが消失する可能性
社員の操作ミスや不正な操作などによって、NASに保存された業務データが消失してしまう恐れもあります。また、NASをはじめとしたHDDの寿命は3~5年と言われていますが、利用環境によってはそれより前に故障してしまう可能性もあるでしょう。
予期せぬ故障や機器のトラブルでデータが失われてしまうことは珍しくないので、重要なデータを管理する場合は、必ずバックアップを取っておくようにしましょう。おすすめのバックアップ先は後述します。
機器の盗難による物理的な情報流出の可能性
NAS本体は比較的小型で持ち運びやすいため、物理的な盗難のリスクも考慮する必要があります。万が一、NAS本体が盗難に遭えば、内部に保存されている全てのデータが流出してしまいます。オフィスへの侵入者による盗難だけでなく、内部関係者による持ち出しの可能性もゼロではありません。
NASのセキュリティ対策法

それでは、NASを安全に運用するために必要なセキュリティ対策を解説していきます。
マルウェア対策
NASでもっとも有効なマルウェア対策は、パソコンと同じように対策ソフト(セキュリティソフト)を稼働させておくことです。
一般的なHDDとは違い、NASはOSを搭載しているため、セキュリティソフトを導入できる製品が多く、さらに独自のセキュリティ機能を持っているものもあります。とくに大人数が利用する環境では、マルウェア対策機能を持ったNASの導入がおすすめです。
クラウドストレージFileforceの資料をダウンロードする。
ぜい弱性への対策
情報セキュリティ分野における「ぜい弱性」とは、プログラムのミスやバグなどによるセキュリティ上の欠陥ことを言います。
いわゆる「セキュリティホール」のことであり、外部からの不正アクセスやサイバー攻撃は、システムやアプリケーションのぜい弱性を狙って行われることが多いです。そのため、しっかりと対策しておかなければいけません。
NASの場合、ファームウェアと呼ばれる制御用プログラムが内部で動作しており、定期的に更新して、ぜい弱性をカバーする必要があります。製品によってはファームウェアの更新が不要な場合もあるようですが、基本的には常に最新の状態にしておくことが大事です。
情報漏えい対策
社員の操作ミスや内部不正による情報漏えいを防ぐためには、ファイル共有に関するルールの策定や厳格なアクセス管理が必要です。
誰でも自由にNASにアクセスできる環境だと、悪意のある者が不正にデータを持ち出す可能性があるからです。必ずアクセス権限設定をしておき、部外者が特定のファイルにアクセスできないようにしておきましょう。
NASの設定ミスによって数万人分の個人情報が外部から閲覧できる状態になっていた事例もあるので、利用者一人ひとりが正しいファイル管理法を覚えるとともに、管理体制に問題はないか定期的にチェックする必要があるでしょう。
不正操作対策
情報漏えい対策の一環でもありますが、内部からの不正操作を防ぐためにアクセスログの取得・管理も必要でしょう。
NASにはアクセスログ管理機能が実装されている製品も多いので、多くの社員がアクセスする環境を構築する場合、ログ管理機能が搭載されたNASの導入をおすすめします。不正アクセスの検知やファイルの削除や改ざんを防止できる機能を持った製品もあります。
物理的な盗難対策
NASの物理的な盗難に対する備えも必要です。保存データを暗号化しておき、盗難に遭った場合に情報の流出を防ぐ対策はもちろん、HDDの盗難防止用のワイヤーロックなどを使用して、設置場所から持ち出されないようにしておきましょう。とくに大企業の場合、機器の置き場所は管理部門しか分からないようにしておくことも大事です。
NASで重要なバックアップ対策

どれほどセキュリティ対策を万全にしても、NASに保存されたデータを100%守れるとは限りません。NAS自体が故障してしまう可能性もあるので、万が一に備えて保存データのバックアップを取っておくようにしましょう。
また、データのバックアップ方式は主に次の3種類があります。 いずれの方法でもバックアップが可能なので、自社に合った方法を選択しましょう。
| バックアップ方式 | 概要 | 注意点 |
|---|---|---|
| ファイルバックアップ | 必要なファイルやフォルダだけをコピーし、変更があれば更新する方式。必要なデータを素早く復旧できる。 | 全体の復旧には不向きで、個別設定が必要。 |
| イメージバックアップ | データ全体をイメージファイルとして保存し、圧縮で容量を節約できる。 | 復元に時間がかかり、必要なデータを抽出する手間がある。 |
| レプリケーション(複製) | 複数のNASを連携させ、メイン機のデータを自動でバックアップ機に同期する方式。手間が少なく自動化に優れる。 | 複数のNASの導入コストや初期設定が必要。 |
NASのバックアップ方法
 続いて、NASのバックアップ先と具体的なバックアップ方法を解説します。
続いて、NASのバックアップ先と具体的なバックアップ方法を解説します。
ローカル環境にバックアップする
NASのデータを他のHDDやSSDにバックアップしている企業は多いでしょう。HDDは導入コストが安く大容量データの保存にも適しているため、ビジネス規模に関わらず広く活用できます。あるいは上記のレプリケーションで説明したように、NASを複数台導入することでファイル管理用とバックアップ用を使い分ける方法もあります。
ただし、HDDは平均して3~5年で寿命を迎えるため、定期的に機器の交換が必要になることを忘れてはいけません。定期的に動作状況のチェックを行い、予期せぬ故障が起こらないよう注意しましょう。熱や湿気、ほこりにも弱いため、設置場所も考慮する必要があります。
RAIDを活用してバックアップ領域を作成
NASはRAIDと呼ばれる複数のHDDを一つのドライブのように扱う技術が使われています。データを複数のディスクに同時に保存することで、1本のHDDが破損しても、別のHDDに保存されたデータを使って復元ができる場合も。
とくにRAID5やRAID6のレベルではHDDが4台内蔵されており、前者は1台、後者は2台分のHDDが故障してもデータの復旧できる可能性があります。より強固なリスク対策を構築したいのであれば、導入を検討しても良いでしょう。
ただしRAID機能だけに頼るのではなく、NASが物理的に損傷を受けたり、寿命を迎えたりした場合に備えて、別の記憶媒体にデータのバックアップを取っておくことが大事です。
クラウドストレージを利用する
クラウドストレージは、NASのバックアップ先としても有効な選択肢です。データは遠隔地のデータセンターに保管されるため、災害などで社内のHDDが損傷しても安全性が高く、事業継続に役立ちます。契約後すぐに利用でき、必要に応じて容量を柔軟に増減できる点も魅力です。また、インターネット環境があれば端末を問わずアクセスできるため、バックアップだけでなくメインのファイル管理にも活用可能です。法人向けのクラウドストレージはセキュリティ対策も万全で、通信データの暗号化により機密情報も安全に扱えます。
おすすめのクラウドストレージ「Fileforce」

最後に、NASのバックアップ先としても利用できる、おすすめのクラウドストレージとして「Fileforce」をご紹介します。
「Fileforce」は強固なセキュリティと自由度の高いアクセス権限設定が特長の法人向けクラウドストレージです。ビジネス規模を問わず導入が可能で、これまで自社で利用していたファイルサーバーの形態に準拠した運用が可能です。
細かいユーザー権限の設定が可能で、フォルダやフォルダに対する権限を一元的に管理できるため、複雑な組織構造を持つ企業でも全社的なファイル管理ができます。導入を前提とした検証用アカウントで使い勝手を試すことができるので、実際にサービスを体験してみましょう。
クラウドストレージFileforceの資料をダウンロードする。
まとめ
NASのセキュリティ強化の必要性と、具体的な対策を解説しました。NASの導入に当たっては、必ずセキュリティ対策が必要になります。必要な対策を怠ると、マルウェア感染や情報漏えい、不正操作や盗難といったセキュリティ事故が発生する可能性があります。
実際、セキュリティ事故を起こしてしまった組織も存在するため、セキュリティソフトの導入やデータの暗号化、不正操作対策など、基本的な対策はしておきましょう。加えて、大事なデータは必ずバックアップを取っておくことも重要です。
とくにクラウドストレージは導入のしやすさや利便性、リスク分散の観点から非常にバランスの取れたサービスなので、バックアップ先としてはもちろん、企業のファイルサーバーとしてもおすすめです。
クラウド化を推進したいけどセキュリティ面が不安...とお考えの方へ
インターネットからアクセスできてしまうと、外部からの攻撃を受けやすくなるのでは?クラウド化したときの安全性はどうなるの?と不安に思われる方もいるかもしれません。
クラウドストレージでのセキュリティ対策についてまとめた資料をご用意いたしました。ぜひご参照ください。